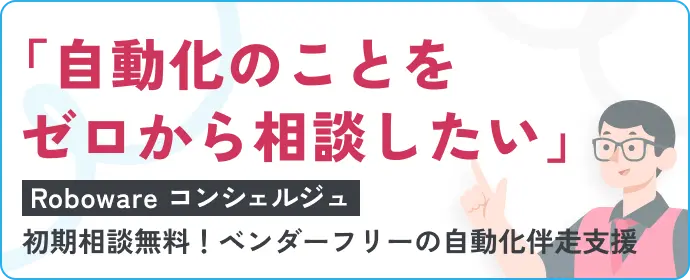最終更新日:2024.05.17
公開日:2021.07.28
- #基礎知識
WMS(倉庫管理システム)とは?導入メリット・デメリットを紹介!
はじめに
WMS(倉庫管理システムまたは在庫管理システム)とは、物流センター内の一連作業に欠かせないソフトウェアです。WMSは、製造業・卸売業・小売業・食品・通販・ECなど業界問わずに様々な倉庫で使われています。この記事では、WMS(倉庫管理システム)の特徴や導入メリット・デメリットについて紹介します。
WMS(倉庫管理システム)とは

WMS(倉庫管理システム)とは、Warehouse Manegement Systemの略で、この頭文字をとってWMSと呼ばれることが一般的です。
入出庫管理や在庫管理などをデジタル化できるシステムのことです。
倉庫内作業を従来のアナログな手法だと効率化がより求められている物流業界では限界があります。工数削減のためにWMSは倉庫内の作業をスピードアップさせるには欠かせないソフトウェアです。
WMSは、製造業・小売・卸・EC物流など幅広い企業で導入されています。
WMSの主な機能
WMSには次のような基本機能があります。
1.入荷管理
商品の入荷を管理する機能です。入荷予定リストを使ってどのような商品が何個入るのかを確認し、実際に入ってきた在庫を記録できます。加えて、入荷した商品を素早く検品するための入荷検品機能なども搭載されています。
2.在庫管理
リアルタイムに在庫情報を管理できる在庫管理機能もWMSの機能のひとつです。在庫照会やロケーション(商品の保管場所)移動、廃棄や補充、ロット管理など、在庫に関するあらゆる処理をWMS上で行えます。
3.出荷管理
出荷全般を管理するための出荷管理機能です。出荷予定の注文を確認したり、注文に基づいてピッキングリストを出力したりできます。在庫の引き当ても同時に行えるので、在庫の反映をし忘れるリスクが減少して正確な在庫管理を行うことにもつながります。
4.棚卸管理
棚卸業務を行う際に効率化をはかるために導線を指示したり、棚卸の結果差異が出た在庫を一覧表示する「棚卸差異リスト」を出力したりする機能です。ハンディターミナルを導入してバーコードをスキャンすると、WMSと連動して自動的に棚卸結果が記録されます。人の手で行うと膨大な時間がかかる棚卸作業を大幅に効率化できます。
5.帳票・ラベル発行
各種帳票やラベルの発行をシステム上から手軽に行える機能です。注文に基づいて自動的に情報を入力する機能なども備わっているので、1から入力する手間を削減できます。納品書や梱包明細書、各配送事業者別の送り状、値札や荷札などの発行に対応しているケースが多いでしょう。
6.返品管理
出荷先の都合で商品が倉庫に返送されてくることがありますが、WMSには返品商品を管理する機能も搭載されているため比較的手間なく把握することができます。返品予定データに基づいて返品商品のバーコードをスキャンすると、返品商品を簡単に記録してリスト化できます。
WMSと基幹システム・在庫管理システムの違い

基幹システムや在庫管理システムと似たようなシステムがあり間違えられがちですが、厳密にはWMSとこれらのシステムは異なります。
基幹システムは、多くの企業が導入しています。企業で統一されたシステムで倉庫業務のサポートが網羅されているものではなく、現場の状況を把握できません。WMSには「入出庫業務もカバーしている」という特徴があります。 倉庫の管理方法は、倉庫によって異なるので倉庫管理はWMSが有効です。
WMSにも在庫管理の機能がありますが、倉庫「内」の在庫情報や人員の管理がメインとなるものです。在庫管理システムは在庫管理に特化した仕組みであり、倉庫「外」を含めた在庫情報を管理することができます。WMSと比較するとピッキングの導線管理など倉庫業務効率化の機能が多く搭載されているという点で異なっています。
WMS導入メリット
WMSのメリットは大きく以下の4つです。
1、倉庫内業務を効率化・標準化
WMSの導入によってこれまでアナログで行っていた作業の多くを自動化できるので、倉庫内作業の大幅な効率化が期待できます。
誰が作業を行っても一定レベルの生産性が保たれるように設計されています。例えばピッキングの最適な導線は経験豊富な従業員の熟練技術に頼るケースが多いですが、WMSを利用すると自動的に最も効率よくピッキングを行える導線を算出・指示してくれ、属人化した倉庫業務の標準化・効率化を図れます。
物流では、各庫内作業への所要時間圧縮が全体の作業時間に大きく影響しますので、WMSによる業務効率化は有効な手段の一つと言えます。
2、現状の情報を可視化できる
WMSで在庫管理や流通管理を行うことによって、これまで見えにくかったヒトやモノの流れを可視化でき自社の現状が把握しやすくなります。
例えば庫内作業でミスが発生した際に、どの作業担当者が行ったのか、どんな作業を実施したのかがひと目で分かるので、ミスの原因が分かり、対策を立てやすくなるでしょう。
さらに注文別の処理状況をすぐにチェックできるため、作業が予定通りに進んでいるか、遅れているのであれば何が原因になっているのかをスムーズに導き出せます。
3、クラウド化で情報を共有できる
帳簿をアナログで管理している倉庫では、複数人が在庫情報や注文情報を同時にチェックするのは難しい状況にありました。しかしクラウドを使ってインターネット上で情報を管理できる環境を整えられれば、同時に複数の従業員が物流業務に関わる情報を共有できます。タブレット端末などを導入することで現場にいながら情報を把握できるため、業務効率化を達成できます。
4、ミスを減らせる
人の手で処理すると、どれほど注意していてもヒューマンエラーを0にすることは難しいといえるでしょう。しかしWMSでは機械が処理するため正確性が上がり、ミスを大幅に減らすことが期待できます。
配送ミスは顧客からの信頼を大きく低下させる要因になるので、ミスを減らせるWMSの導入は非常に効果的といえます。
WMS導入のデメリット
WMS導入のデメリット
WMS導入はメリットだけではなく、デメリットもあります。
1、導入コストと時間がかかる
WMSの導入で、日々の物流業務の効率化や標準化に繋がりますが、システムを導入するにはコストと時間もかかります。WMSの使用者にも、使いこなすまでの教育時間も必要になります。本稼働までに少し時間がかかるので計画的に導入の検討をおすすめします。
WMSの選び方

WMSを導入する際の選び方について紹介します。
1、業界・業種との相性
契約を検討している事業者が自社の業界や業種に理解があるかどうかは、重要なポイントです。導入事例をチェックして、同業他社の案件を扱ったことがあるかをチェックしておきましょう。
あわせて実際に倉庫を見てもらい、どのようなサポートを受けられそうか確認しておくことも大切です。
2、使用する目的が果たしているか
なぜ自社がWMSを導入したいのかをはっきりさせておき、その目的を果たせるシステムかどうかを十分に検討しましょう。
そもそもWMSを導入する目的が不明瞭なままだと不適切なシステムを選んでしまい、結果的に導入コストだけがかかって成果を挙げられない可能性もあります。「WMSを使って自社のどの課題を解決したいのか」を明確に意識しておくことが大切です。
3、コストや予算
導入するWMSのコストと自社がシステム導入にかけられる予算のバランスをはかることも重要です。
安さだけを追い求めてしまうと必要な機能が用意されておらず、使い勝手が悪いために社内に浸透しない可能性があります。一方で不要な機能まで搭載されているとシステムが複雑になるばかりか、コストがかかりすぎる恐れもあるので、両方のバランスが取れたシステムを選びましょう。
4、クラウド型かオンプレミス型か
WMSには大きく分けてクラウド型かオンプレミス型の2つのタイプがあります。自社の状況によってどちらが適しているかは異なるので、十分に検討した上で都合の良い方を選びましょう。
●クラウド型
クラウド型は既に事業者が作り込んだ状態のシステムに対してIDやパスワードを発行してもらい、インターネット上でログインして利用する方法です。
1からシステムを開発する必要がないので導入費用を抑えやすく、比較的早い段階で利用を開始できるのがメリットです。一方で、独自機能などの自由なカスタマイズがしにくいというデメリットもあります。
●オンプレミス型
オンプレミス型は自社でサーバーを購入し、社内に設置してWMSを運用する方法です。
拡張性やカスタマイズ性は高く、自社の運用に合わせたシステムを作り上げやすいのが特徴ですが、コストはクラウド型に比べて高くなりやすいというデメリットもあります。加えてある程度まとまった開発期間が必要となるため、導入まではクラウド型よりも時間がかかります。
まとめ
Related Articles 関連記事