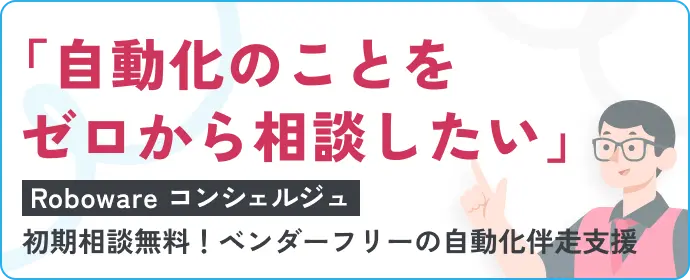最終更新日:2023.12.11
公開日:2021.07.08
- #基礎知識
物流の2024年問題とは?
はじめに

物流業界の2024年問題とは、トラックドライバーの年間労働時間の上限が設けられたことを始めとした物流を取り巻く環境の問題の総称です。労働力不足だけではなく災害対策など多様な課題を抱えており、課題への対策が急務となっています。
物流業界の課題を解決するには現状の把握をし、どのような対策を講じる必要があるか整理しなければなりません。そしてIT技術が進歩している今、AIやロボットを導入して課題解決をはかる動きが加速しています。今回、この記事では課題の把握と対策方法についてご紹介します。
2024年問題によってドライバー拘束時間が変わる
物流業界の2024年問題で大きく影響を受けているのは、働き方改革法案の施行でトラックドライバーの労働時間に上限が設けられたことです。トラックのドライバーは、人手不足の影響もあり一人あたりの労働時間が長くなる傾向で問題とされていました。働き方が改善される一方、人手不足は解消されていないのでモノを運ぶ時間が減少してしまいます。
下記の図とともに、具体的な拘束時間の比較をしていきましょう。現行と2024年4月以降の1ヶ月の労働時間の比較となります。
年間の労働時間の上限が960時間に定められたので、その時間内に収める1ヶ月あたりの労働時間目安を示したものです。
労働時間が減少しただけではなく60時間以上の割増賃金率も50%に上がっているのでコストの増加もポイントになってきます。

厚生労働省が発表している「令和3年度 自動車運転者の労働時間等に係る実態調査結果」では、1か月の拘束時間が274時間を超える事業者は全体の約34%を占めています。その中でも月間320時間を超える事業者が 2.4%もあります。
長距離運行ほど長時間労働の傾向があり、月間275時間以上の事業者が約43%、月間320時間を超える事業者は4.6%もあります。規制の限度内に抑えるには厳しい事業者が存在するのが現状です。
2024年問題で生じている物流業界の課題

現代の物流はさまざまな要因によって多くの課題を抱えています。働き方改革でドライバーの労働時間に上限が課されることだけが問題ではありません。そこで、まずは物流における現状と課題について解説します。
労働力不足
物流業界は、トラックのドライバーだけではなく倉庫作業者を含め深刻的な人手不足の課題が挙げられます。人手不足は、業務の遅延だけではなく品質の低下、物流業界全体に悪影響を及ぼします。特に長距離のトラックドライバーは、一人ひとりへの負担が大きくキャパオーバーになり、働き方改革関連法施行により時間外労働の上限規制等が適用されます。これにより更に稼働率が減少し、必要なときに供給ができなくなる社会問題にも発展していきます。
また日本では少子高齢化が進み、65歳以上の人口が全体の29%までに上っています。※1
ドライバーの平均年齢も上昇し、若い世代のドライバーが育たないことも今後、見過ごせません。この深刻的な人手不足は、物流業界の働き方改革や業界全体のイメージ改革も必要です。
※1 参考:内閣府「令和5年版高齢社会白書」
物流量の増加
誰もがパソコンやスマートフォンを所有するようになり、EC市場が活性化して現在では一般消費者一人ひとりが気軽にインターネットを通じてショッピングするようになりました。そのような背景もあって物量は増加し続けており、令和4年度には宅配便取扱個数が50.5億個にまで到達しています。
10年前の平成24年度には約35億個だったことを考えても、10年間で15億個もの荷物が増加していることになります。
しかし、この激増した荷物を運ぶための従業員は少子高齢化などに起因する人手不足で十分に確保できていません。企業努力だけでは解消できないために利用者への負担増を実施せざるを得ない状況にあり、労働力不足が社会問題化しているのが実情です。
参考:国土交通省「令和4年度 宅配便取り扱い実績」
災害による物流網の脆弱性
近年では台風や地震など自然災害が激甚化しており、より頻回になっています。災害が起こると物流の流れが停滞し、大幅な配送遅延等の被害が起こる可能性が想定されるでしょう。国土交通省が2019年にまとめた「今後の災害・物流ネットワークについて」では、熊本地震の際に県内の緊急輸送道路2,000kmのうち50箇所で通行止めが発生したことを課題に挙げています。
「災害時に道路について不安がある・やや不安がある」と答えた人は53.8%にものぼり、災害が起こった際の物流ネットワークをどのように担保するかは重要な課題となっています。
参考:国土交通省「今後の災害・物流ネットワークについて」
国際物流を取り巻く環境変化
国内物流だけではなく、越境ECも浸透してきており国際物流も年々右肩上がりに発展を続けており、特に2007年頃を境に日本の貿易額はアメリカより中国の方が上回るようになりました。これにより、欧米だけでなくアジアへの物流需要は急激に高まっているといえます。
加えて世界的にみると、気候変動によって従来は輸送ルートに選べなかった北極海航路が夏期に航行できるようになっています。さらに航路の拡張によって新パナマ運河が利用可能になっているなど、貨物の輸送ルートも変化しているといえるでしょう。
2008年から2018年の間に世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は1.5倍にまで増加しており、日本だけでなく世界でも海運、空運ともに輸送需要は高まっています。越境サプライチェーンが一体的に構築されているアジア圏での物流競争から取り残されないためにも、国際的な動きに取り残されない物流体制を構築しなければならない状況にあるといえます。
物流業界の今後の対策案

ここまでにご紹介した物流の現状や課題を踏まえて、物流業界が今後取る必要のある対策について解説します。
物流のデジタル化の推進
IT技術の発展に伴って、ロボットやシステムを利用して業務を効率化できる可能性は大きく広がったといえます。しかし国内ではまだアナログで物流業務を行う事業者も多く、デジタル化を積極的に推進していくことが課題になるでしょう。
デジタル化を進めるにあたって従業員の無理解や抵抗感がネックになるケースも多いので、まずは社内でデジタル化の目的を明確にして、従業員に主旨を理解してもらうための準備を整えることが大切です。
デジタル化やロボットの活用を推進すると、従業員からは自らの職が奪われるのでは?給料が減らされてしまうのでは?という不安が必ず発生します。しかし、デジタル化をすることで職を奪うのではなく効率化し生産性と品質を高めていく行動であることの周知と理解が必要です。また、デジタル化やロボットの導入を検討していくことは大きな設備投資となります。採算性やどのくらいの年数で回収できるか等の計画も必要となってきます。
労働力不足解決のための、自動化・機械化
前述の通り、日本国内では高齢化社会が進んでいき人口減少からの労働力不足が避けられないとみられています。労働力不足を解消するために物流業務の自動化や機械化を進めていく必要があります。
人口が減少して立ち行かなくなってから対応しようとするのではなく、日頃から少しずつ準備を進めることでスムーズに将来の人口減少に対応できます。
WMSやハンディターミナルの導入など、まずは身近な業務の自動化から始めるのがおすすめです。ロボット導入に関しても、現状のレイアウトやオペレーションを大きく変更せずに実現できる仕分け・ピッキングといった作業フローの後工程から改善していくこともおすすめします。自動化や機械化が労働力不足のための解決策ではなく、品質やパフォーマンスの安定化に繋がっていきます。
物流人材の育成・確保
物流需要が高まり続けている現状ですが、人手不足から十分な物流人材を育成できているとは言い難い状況にあります。将来の物流の担い手となる物流人材を育成・確保することも、安定的な物流を提供する上では必要不可欠です。物流業界全体のイメージも変えていかなければなりません。現状の物流業界は決して表に出て華やかなイメージを持たれる業界ではないことは事実です。
しかし、今後も物流業界が生活インフラを支える非常に大事な位置づけであることは変わりません。
物流人材を育成し、自社の問題点を見極めて改善につなげたり新たなビジネススタイルを生み出したりできる人材を確保することで、業務効率の向上にもつながり良い循環を生み出します。
世界の物流情勢や課題解決方法
世界的にも需要の増加が著しい物流業界ですが、世界ではどのように対策しているのでしょうか。ここで具体的に解説します。
ロジスティクス4.0
これまでのロジスティクスは、トラックなどの配送車を使って物流を機械化する「ロジスティクス1.0」、クレーンやベルトコンベアを使って荷役を機械化した「ロジスティクス2.0」に続いて、WMSなどを導入して物流管理を機械化する「ロジスティクス3.0」にまで到達しています。
そして今、人手不足など新たな課題を解決するために物流は「AI」と「IoT」を駆使した「ロジスティクス4.0」へ移行しつつあります。ロジスティクス4.0が物流がひっ迫しつつある現状を解消する鍵になるといわれています。
省人化
ロジスティクス4.0では「ロボットによる判断」が可能になることから、物流業務の省人化が期待できます。例えばドローンで目的地に商品を配送したり、配送トラックを自動運転したりなどドライバー不足の解消法が考えられるでしょう。加えて倉庫の作業ロボットを実用化できれば、ピッキングや梱包などの庫内業務の省人化も実現できます。
これまでは人がいなければ操作や判断が難しかった業務でもAIによって機械が判断できるようになれば、人の手を介さずに業務を遂行できる可能性が高まります。
標準化
現代ではさまざまなデータにあふれており、データの有効活用が業務効率化の大きな助けになるといわれています。配送車両や商品そのものをインターネットと連携して管理すれば、モノの流れがリアルタイムで把握できるようになるでしょう。
これらのデータを長期間蓄積して機械に学習させることで、より効率的な配送ルートを導き出せるようになります。このように人間が考えなくても物流を最適化できるようになれば、人によって異なる判断がなされることを防いで業務の標準化をはかれます。
日本でも物流システムの見直しが必要
日本国内においてはまだまだ物流業務をアナログで進めている企業も多く、人の手に依存して成り立っている現場は数多くみられます。
人手不足がますます深刻化し物流需要は増加していくことが見込まれている以上、今後は日本においても物流システムの見直しが必要になるでしょう。物流業界全体が自分ごととして捉えて対策を重ねることで、業界全体の業務効率が改善します。
AI・ロボットの活用が物流の鍵となる
WMSやハンディターミナル等、業務を自動化するシステムは現状でも導入している企業は多いといえます。
しかし今後はAIやロボットを活用して「判断・思考」の部分を自動化することが、物流の業務を大幅に効率化する鍵となるでしょう。人間の実作業の負担を最小限に抑え、AIやロボットを管理する側に立てる環境を用意することが重要であるといえます。
まとめ
日本国内においてはまだまだ物流業務をアナログで進めている企業も多く、人の手に依存して成り立っている現場は数多くみられます。
トラックドライバーの労働時間規制だけではなく、その前工程となる倉庫作業を効率化することも必要です。
人手不足がますます深刻化し、物流需要は増加していくことが見込まれている以上、今後は日本においても物流システムの見直しが必要になるでしょう。物流業界全体が自分ごととして捉えて対策を重ねることで、業界全体の業務効率が改善します。
はじめての倉庫ロボットパートナー“Roboware”
はじめての自動化をサポートする倉庫ロボットパートナーRobowareは、直感的な操作で簡単に物流業務を自動化するロボットを提供しています。単なるRPAから一歩進んだ複合的なフレームワークで、スピーディーかつ正確に業務を遂行できます。ロボットの提案だけではなく、既存の自社WMSとの連携ができたり、万が一ロボットに不具合があっても24時間365日サポートする体制も整っています。導入して終わりではなく、導入してからもより効率化、コスト削減できる提案をできることが大きな特徴です。
自動化によりロボットがさまざまな業務を進めてくれるので、従業員の負荷の軽減と人件費をはじめとした物流コストの削減を同時に実現できます。数多くの著名な企業も活用しております。事例集もあわせてご確認ください。
Related Articles 関連記事